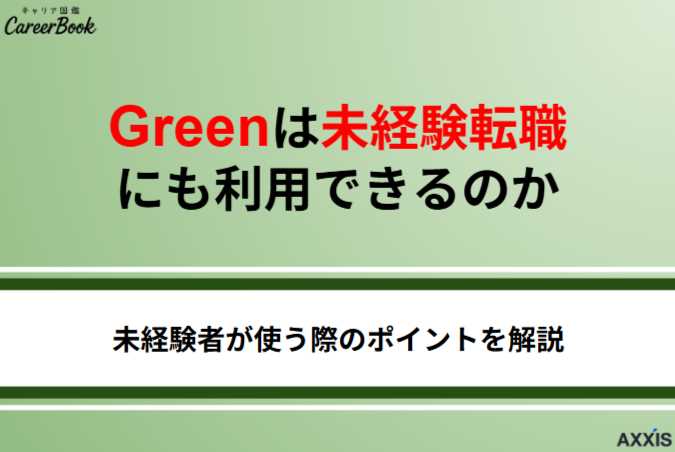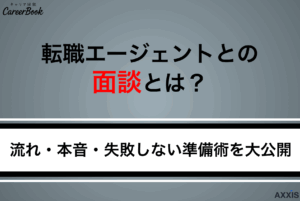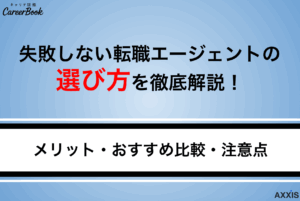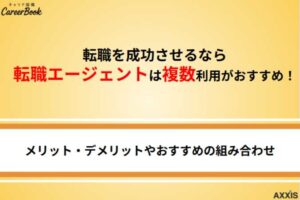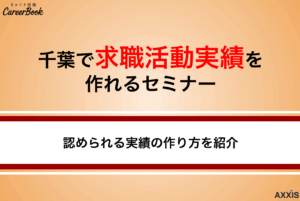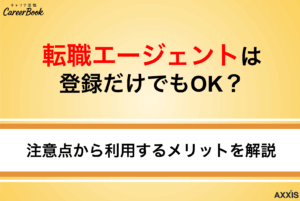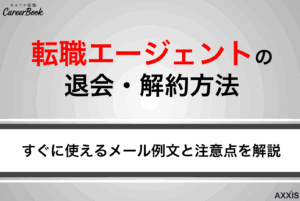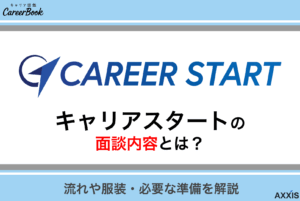Greenは未経験転職でも利用できるのか、理由と共に解説していきます。
さらに、その上でGreenを有効に活用するための具体的なコツから、転職成功の確率を最大化するための転職エージェントとの戦略的な併用まで、キャリア支援のプロの視点で徹底的に解説していきます。
Greenは未経験者の転職に使えるのか
GreenはIT業界に特化した転職サイトであり、IT業界未経験者でも利用はできますが、経験者向けの求人が多く未経験者だと求人を探しにくいです。
実際に、Greenの公式サイトの情報によると、60%以上の利用者はIT系職種経験者となっています。

出典:Green公式サイト
そのため、Greenは未経験者の転職でも利用はできるものの、IT未経験で使いこなすことは難しく、経験者のほうが利用しやすい転職サイトと言えます。
具体的に、GreenがIT未経験だと利用しにくい理由について、解説していきます。
Greenは未経験だと厳しい理由

そのため、IT未経験者は企業が求めている人材について深く理解している、未経験者に特化した転職エージェントや、求人数の多い大手転職エージェントから求人を紹介してもらうことがおすすめです。
20代の未経験でITに転職したい人はUZUZ、30代以降ならリクルートエージェントがそれぞれ未経験者への支援が手厚くIT業界にも強いのでおすすめですよ。
未経験歓迎の求人割合が低い
Greenに掲載されている求人全体の中で、「職種未経験歓迎」や「業界未経験歓迎」とされる求人の割合は、決して多くありません。
GreenはIT・Web業界の経験者や、即戦力となるスキルを持った人材のマッチングに強みを持つプラットフォームです。そのため、企業側も経験者をメインターゲットとして求人を掲載しているケースが多く、未経験者が応募できる求人は必然的に限られてきます。
「なかなか応募できる求人が見つからない」「応募しても書類で落ちてしまう」と感じるのは、そもそも未経験で採用している求人が少ないからです。
企業とのやり取りをすべて自分でおこなう必要がある
Greenは、企業と求職者が直接コミュニケーションを取れるのが魅力ですが、未経験者にとってはこれがかえってハードルになることがあります。
プロフィールの作成から求人探し、応募、面接の日程調整、条件交渉まで、転職活動の全プロセスを自分だけで進めなければなりません。
特に、職務経歴書で自分のポテンシャルをどうアピールすれば良いか、カジュアル面談で何を質問すれば良いかなど、未経験者ならではの悩みや疑問を相談できる相手がいません。手探りで進めるうちに、時間だけが過ぎていったり、的外れなアピールをしてチャンスを逃してしまったりする可能性があるのです。

しかし、自分のどんな経験がITでも活かせるのか、業界や企業のことをあまり知らない未経験者では把握することが難しいです。
なので、周囲のIT・Web業界の知見がある人や、転職のプロである転職エージェントなどに相談しつつ転職活動を進めることがおすすめです。
Greenを未経験者が有効活用する3つのコツ
Greenが未経験者にとって厳しい側面があるのは事実ですが、決して使えないわけではありません。ポイントを押さえて戦略的に活用すれば、未経験者にとっても強力な武器になります。
ここからは、Greenの機能を最大限に活かし、転職成功のチャンスを掴むための3つのコツを紹介します。
Greenを有効活用する3つのコツ
プロフィールを徹底的に充実させる
採用担当者は、毎日数多くのプロフィールに目を通しています。その中で目に留まり、「この人に会ってみたい」と思わせるためには、プロフィールの充実度が非常に重要です。
特に未経験者の場合、実務経験がない分、ポテンシャルや学習意欲を伝える工夫が求められます。必須項目だけでなく、自己PR欄やスキル欄などを活用し、これまでの経験と希望職種をどう結びつけられるかを具体的に記述しましょう。
プロフィールや職務経歴書の登録で意識するべき点は、以下の通りです。
プロフィール・職務経歴書のポイント
- プロフィール欄は必須項目以外も全て記入する
- 経験やスキルは具体的に書く(例:売上向上に貢献→○○という施策で、売上を前年比120%に向上させた)
- これまでの実績を客観的な数字で示す
- 自己PR欄で、入社後の貢献意欲を伝える
- 制作職などで、ポートフォリオを出せる場合は載せておく
- 希望条件を限定し過ぎない(妥協できる条件は記入しない)
例えば、プログラミングスクールで学んだ内容や作成したポートフォリオ、前職で培ったコミュニケーション能力や課題解決能力など、「なぜIT業界なのか」「入社後どう貢献したいのか」という熱意が伝わるように、自分の言葉でしっかりと書き込むことが大切です。
「気になる」とカジュアル面談を戦略的に活用する
Greenの大きな特徴である「気になる」機能や「カジュアル面談」は、積極的に活用するべきです。ただし、やみくもに使うのではなく、戦略的な視点を持ちましょう。
Greenには選考に応募する以外にも、企業と繋がる手段として以下のものがあります。
Greenで企業と繋がる方法
- スカウト:企業が求職者のプロフィールを見て、魅力を感じた人に選考の案内を送る。
- 「話を聞いてみたい」機能:選考に進む前に、企業についてもっと深く知るために、カジュアル面談を申し込める機能。
- 気になる機能:気になった企業にアピールできる機能。企業側は「気になる」を送った求職者が誰か分かるようになっている。
話を聞いてみたいや気になるは、企業側の判断次第でカジュアル面談に進めるか決まります。企業から無視される可能性があることを理解しておきましょう。
「気になる」は、少しでも興味を持った企業へのアンテナとして幅広く送るのがおすすめです。どんな企業が自分に興味を持ってくれるのかを知る、市場価値の調査ツールとしても活用できます。
そして、企業から反応があれば、積極的にカジュアル面談を申し込みましょう。面接とは違うリラックスした雰囲気で、企業のリアルな情報を得られる貴重な機会です。企業の文化や働く人の雰囲気が自分に合うかを見極める絶好のチャンスと捉え、情報収集の場として有効活用してください。
企業の求める人物像を深く理解する
未経験者を採用する場合、企業は現時点でのスキルよりも、今後の成長ポテンシャルや人柄、学習意欲などを重視する傾向があります。
求人票を見る際は、必須スキルだけでなく、「求める人物像」や「歓迎するスキル」の欄を注意深く読み込みましょう。「主体的に学べる人」「チームで協力できる人」といった記述から、企業がどんな人材を求めているのかを深く理解することが重要です。
その上で、自分の経験や強みが、その企業が求める人物像とどうマッチするのかを考え、プロフィールや面談で的確にアピールすることが、内定への近道となります。
未経験者の転職成功率を高めるなら転職エージェントとの併用が最適
Greenを有効活用するコツを実践するだけでも、転職活動の状況は改善されます。しかし、未経験からの転職成功率を最大限に高めたいのであれば、転職エージェントとの併用が最も効果的な戦略と言えます。
なぜなら、転職のプロであるキャリアアドバイザーが、あなただけでは難しい部分を徹底的にサポートしてくれるからです。ここでは、転職エージェントを併用すべき3つの大きなメリットを解説します。
転職エージェントを併用するメリット
客観的な視点で強みやキャリアプランを整理できる
自分だけで転職活動をしていると、「自分の強みは何だろう?」「どんなキャリアを歩みたいんだろう?」といった自己分析が、主観的になりがちです。
転職エージェントに相談すれば、キャリアのプロが客観的な視点であなたとの面談をおこない、自分では気づけなかった強みや価値観を引き出してくれます。
その上で、あなたの希望や適性に合ったキャリアプランを一緒に考え、言語化してくれるのです。キャリアの軸が明確になることで、企業選びや面接でのアピールにも一貫性が生まれ、説得力が格段に増します。
非公開求人を紹介してもらえる可能性がある
転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数保有しています。これらは、企業が戦略的に採用を進めたいポジションや、応募が殺到するのを避けたい人気企業の求人であることが多いです。
Greenだけでは出会えなかった、あなたの希望に合う優良企業の求人を紹介してもらえる可能性があります。
特に、未経験者向けのポテンシャル採用枠は非公開で募集されることも少なくありません。選択肢が大きく広がることは、転職エージェントを利用する大きなメリットの1つです。
書類添削や面接対策で選考通過率が上がる
未経験者が最も苦戦するのが、職務経歴書や面接でのアピールです。実務経験がない中で、いかに自分のポテンシャルや熱意を伝え、企業に「会ってみたい」「採用したい」と思わせるかが重要です。
転職エージェントは、これまで何人もの未経験者を転職成功に導いてきた実績があります。その知見を基に、あなたの職務経歴書を「企業に響く」内容に添削してくれたり、模擬面接を通して、自信を持って本番に臨めるように徹底的にサポートしてくれたりします。
独学で対策するよりも、選考通過率が格段に上がります。
Greenと転職エージェントの効果的な使い分け戦略
「Greenと転職エージェント、両方使うのは大変そう」と感じるかもしれませんが、それぞれの役割を理解し、うまく使い分けることで、転職活動は効率的かつ戦略的に進められます。
Greenと転職エージェントはどちらも異なる特徴を持っているので、両方とも使うことでその強みを引き出せます。
特に、未経験転職を考えている人は、経験者よりも転職市場では不利であるため、その差を埋めるために様々な転職サービスの強みを引き出していくことがおすすめです。
Greenでは情報収集とカジュアル面談で企業理解を深める
Greenは、IT・Web業界の様々な企業を広く知るための情報収集ツールとして非常に優れています。
特に、ベンチャー・スタートアップ企業の求人が豊富なため、IT・Web業界にはどんな求人があるのか分かるため、未経験者が業界の雰囲気を知る際には有用な手段です。
また、Greenにはカジュアル面談を申し込む「話を聞いてみたい」という機能があります。
Greenを使う際には積極的にカジュアル面談を申し込み、企業との接点作りや業界・企業理解を深める場として活用することがおすすめです。まだ応募意思が固まっていなくても、複数の企業の話を聞くことで、自分のやりたいことや合う社風が明確になっていきます。

業界・職種への理解度を上げるためにも、様々な企業から話を聞いてみることがおすすめですね。
その業界や職種への理解度を高めることで、熱意ややる気を企業に伝えやすくなりますよ。
転職エージェントではキャリア相談と選考対策で内定確度を上げる
転職エージェントは内定獲得を達成するための戦略的パートナーと位置づけましょう。
キャリアの方向性が定まったら、プロの視点で具体的な求人を紹介してもらい、職務経歴書の添削や面接対策といった選考を突破するためのサポートを徹底的に受けていきます。
転職エージェントは求人紹介しかされないと思われがちですが、他にも無料で以下のサポートを受けられます。
転職エージェントで受けられるサポート内容
- 求人紹介
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接対策
- 面接などの日程調整
- 企業との給与などに関する条件交渉
- 自己分析のサポート
- キャリア相談
転職エージェントを通して、求人の見方や面接のフィードバックなどを知ることもできます。
自分が面接でやりがちな失敗を客観的に知れることで、エージェント経由以外にもGreenなどの転職サイトから応募した際にも面接の通過率が上がります。
未経験からのIT転職に強いおすすめ転職エージェント
数ある転職エージェントの中でも、特に未経験からIT業界への転職サポートに定評のある転職エージェントを厳選して紹介します。
未経験でIT・Web関連の仕事に転職する場合は、大手転職エージェントか未経験の20代支援に特化した転職エージェントがおすすめです。
未経験者の支援に特化した転職エージェントが最もおすすめではあるのですが、多くの場合は20代しかサポート対象としていないので、30代以降の人は大手転職エージェントを利用することがおすすめです。


大手転職エージェントの多くは、新卒向けにもサービスを展開しているため、その繋がりから未経験者でも積極的に募集している求人を保有しているからです。
年齢や職歴による登録制限も、大手転職エージェントには存在せず、その圧倒的な求人数から誰でも希望に合った求人が見つけられます。以下におすすめの大手転職エージェントをまとめているので、1~2社登録してみましょう。
転職エージェントの選び方について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人は読んでみてください。
Greenの未経験転職に関するよくある質問
Greenの未経験転職に関するよくある質問をまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
Greenは30代未経験でも使えますか?
はい、利用できます。
ただし、20代に比べてポテンシャル採用の枠は少なくなる傾向があるため、より戦略的なアピールが求められます。前職でのマネジメント経験や、異業界で培った専門性をIT業界でどう活かせるかを具体的に示すことが重要です。30代未経験の場合は特に、転職エージェントと相談しながら進めることを強くおすすめします。
IT業界未経験からエンジニアを目指せますか?
目指せます。実際に、Greenや転職エージェント経由で未経験からエンジニアに転職する人は少なくありません。
ただし、プログラミングスクールに通うなど、自主的な学習は必須です。学習意欲やポートフォリオをプロフィールでしっかりアピールすることが、選考を突破する鍵となります。
利用していることが会社にバレる可能性はありますか?
Greenには、特定の企業に対してプロフィールを非公開にする「ブロック機能」があります。
現在の勤務先や関連会社を登録しておくことで、あなたの情報が閲覧されるのを防げます。この設定を最初におこなっておけば、会社にバレるリスクは非常に低いです。
企業からの返信率はどのくらいですか?
返信率は、あなたの経歴やスキル、そして企業の採用状況によって大きく変動するため、一概には言えません。一般的には、経験者向けの求人が多いため、未経験者の場合の返信率は決して高くないと認識しておきましょう。返信がないことに一喜一憂せず、淡々とアプローチを続ける姿勢が大切です。